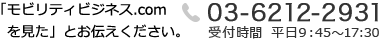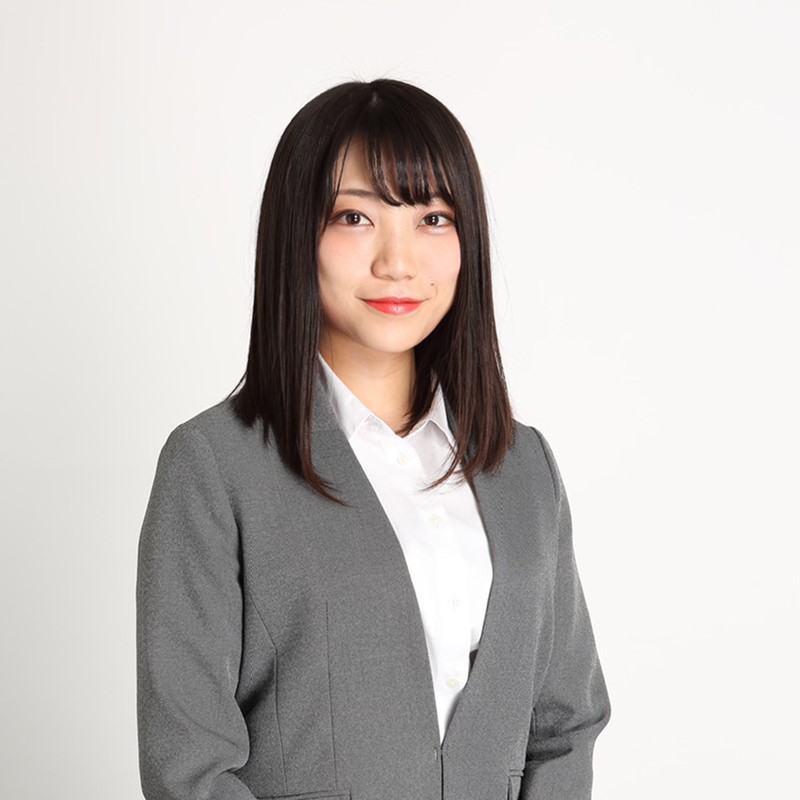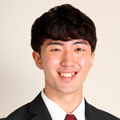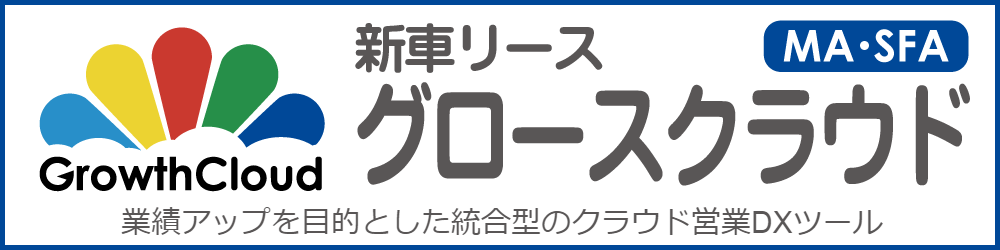-

田村 達朗
2024.04.18
業績アップコンサルタントコラム
SS企業注目!中古車販売店への業態転換で売上1.8倍&粗…
いつもお世話になっております。 船井総研の田村です。 本日は大阪を拠点に、元々ガソリンスタンドを…
MORE
-

堀 和紀
2024.04.18
業績アップコンサルタントコラム
生産性を最大化するデジタル管理ツールをご存知ですか?
いつもお世話になっております。 船井総研の堀です。 本日は、昨今ご相談が増えている「管理業務の生…
MORE
-

文野 陽太
2024.04.16
業績アップコンサルタントコラム
軽中古車業界 繁忙期の振り返り
皆様、こんにちは。 株式会社船井総合研究所の文野です。 本日は、「軽中古車業界 繁忙期の振り返り…
MORE
-

新村 雅也
2024.04.10
業績アップコンサルタントコラム
赤字だったSS店舗が独自の洗車サブスクで粗利2.7倍を実…
いつもお世話になっております。 船井総研の新村です。 本日は東京の昭島市や八王子市でガソリンスタ…
MORE
-

加藤 智
2024.04.09
業績アップコンサルタントコラム
簡単!すぐできる! 自動車販売店が新規集客を増やすための…
平素よりお世話になっております。 船井総合研究所の加藤智です。 今回は一昨年のコラムで多くの反響…
MORE
-

文野 陽太
2024.04.09
業績アップコンサルタントコラム
いくつ当てはまる?【理想の中古車販売店繁盛度チェック】貴…
いつもお世話になっております。 船井総合研究所、モビリティ支援部の 文野陽太でございます。 お忙…
MORE
-

モビリティビジネス経営研究会
2024.04.05
業績アップコンサルタントコラム
【必見】人事評価制度を見直すタイミング
いつもご愛読いただきありがとうございます。 船井総合研究所の松尾です。 最近では採用で悩んでいる…
MORE
-

新村 雅也
2024.04.02
業績アップコンサルタントコラム
SS店舗から洗車&コーティング専門店への業態転換で粗利3…
いつもお世話になっております。 船井総研の新村です。 本日は京都でガソリンスタンドを9店舗展開す…
MORE
-

新村 雅也
2024.03.29
業績アップコンサルタントコラム
『SS企業注目!赤字だった店舗が洗車のサブスクで粗利2.…
いつもお世話になっております。 船井総研の新村です。 本日は東京の昭島市や八王子市でガソリンスタ…
MORE
-

堀 和紀
2024.03.25
業績アップコンサルタントコラム
実はあまり知られていない「人手をかけず」問い合わせを増や…
いつもお世話になっております。 船井総合研究所モビリティ支援部の堀です。 今回は、当メールマガジ…
MORE
-

遠藤 圭太
2024.03.18
業績アップコンサルタントコラム
新車リース販売店が繁忙期を攻略するために②
平素よりお世話になっております。 船井総合研究所 モビリティ支援部の遠藤です。 日頃は全国の新車…
MORE
-

新村 雅也
2024.03.15
業績アップコンサルタントコラム
【開催レポート!】2024年3月度 ガソリンスタンド経営…
いつもメルマガをご購読いただき誠にありがとうございます。 船井総研の新村です。 本日は3月13日…
MORE
-

遠藤 圭太
2024.03.15
WEB集客コンサルタントコラム
【新車販売店必見!】 チラシを使わなくてもお客様が来る!…
平素よりお世話になっております。 船井総合研究所 モビリティ支援部の遠藤です。 日頃は全国の新車…
MORE
-

新村 雅也
2024.03.15
業績アップコンサルタントコラム
SS企業注目!洗車&コーティング専門店への業態転換で粗利…
いつもお世話になっております。 船井総研の新村です。 本日は京都を本社に構えて、ガソリンスタンド…
MORE
-
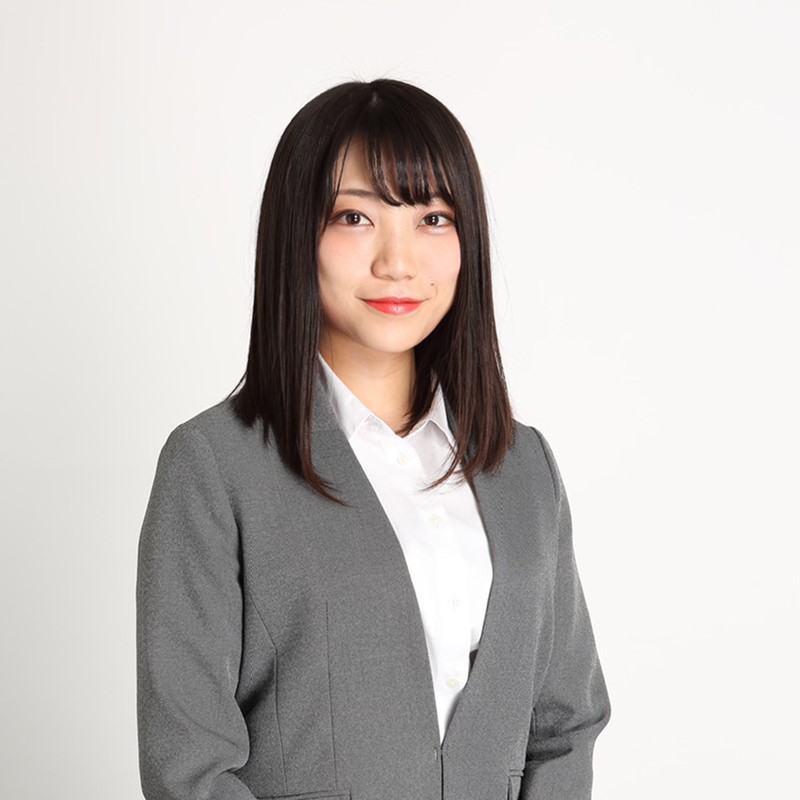
岡田 三菜美
2024.03.12
業績アップコンサルタントコラム
【実績好調な新車販売店がやっている】成功事例3選!
モビリティビジネスニュースをご覧いただいている皆様、いつもありがとうございます。 船井総合研究所…
MORE
-

文野 陽太
2024.03.08
業績アップコンサルタントコラム
繁忙期成功事例ピックアップ
いつもお世話になっております。 船井総合研究所 文野でございます。 いつもメルマガをご愛読いただ…
MORE
-

モビリティビジネス経営研究会
2024.03.07
業績アップコンサルタントコラム
【最新】Web集客の最大化!自動車販売ビジネス別攻略法大…
いつもメルマガをご愛読いただき、ありがとうございます。 船井総研 竹花大貴(たけはな ひろき)で…
MORE
-
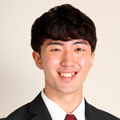
宮原 拓司
2024.03.04
業績アップコンサルタントコラム
中小企業のレンタカー事業が陥りやすい落とし穴と成長のため…
いつもお世話になっております。 株式会社 船井総合研究所の宮原です。 今回のコラムでは、 中小企…
MORE
-

モビリティビジネス経営研究会
2024.03.01
実況中継コンサルタントコラム
< 車検倍増セミナー2024 年 >
2024 年2月19日(月)大阪本社 2024 年2月19日(月)、船井総合研究所 大阪本社にて…
MORE
-

浜中 健太郎
2024.02.29
WEB集客コンサルタントコラム
【2024年最新版】整備工場のWeb集客
皆様、平素より大変お世話になっております。 モビリティ支援部の浜中でございます。 メルマガをお読…
MORE
-

服部 憲
2024.02.29
業績アップコンサルタントコラム
「出店」か「異業種」か「DX」か!?自動車販売店の成長戦…
モビリティビジネスニュースをご覧いただいている皆様、いつもありがとうございます。 船井総合研究所…
MORE
-

文野 陽太
2024.02.26
業績アップコンサルタントコラム
中古車販売モデル企業 業績アップの秘訣
いつもお世話になっております。 船井総合研究所 文野でございます。 いつもメルマガをご愛読いただ…
MORE
-

淵上 幸憲
2024.02.26
業績アップコンサルタントコラム
まだ間に合う!!【3月4日・8日・11日オンライン開催!…
いつも弊社のブログをお読みいただいている皆様 ありがとうございます。 私、株式会社船井総合研究所…
MORE
-
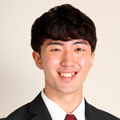
宮原 拓司
2024.02.22
業績アップコンサルタントコラム
郊外のレンタカー屋がどうやって売上2億を達成したのか?!…
いつもお世話になっております。 船井総研の宮原です。 本日は4月3日(水)開催の「長期レンタカー…
MORE
-

新村 雅也
2024.02.20
業績アップコンサルタントコラム
『SS企業向け洗車&コーティングで油外収益アップ!話題の…
いつもお世話になっております。 船井総研の新村です。 本日は17日のメルマガでもご紹介させていた…
MORE
-

加藤 智
2024.02.15
業績アップコンサルタントコラム
<マイカーリース取扱店向け> 〖最新トレンド〗「マイカー…
いつもご愛読いただきありがとうございます。 モビリティ支援部 MaaS事業開発グループ マネージ…
MORE
-

新村 雅也
2024.02.15
業績アップコンサルタントコラム
『今、SS業界で話題の豪華ゲスト企業登壇!ガソリンスタン…
いつもお世話になっております。 船井総研の新村です。 本日は新たにガソリンスタンド企業様向けに開…
MORE
-

文野 陽太
2024.02.07
業績アップコンサルタントコラム
軽中古車専門店の1月実績速報
いつもお世話になっております。 船井総合研究所 文野でございます。 いつもメルマガをご愛読いただ…
MORE
-

モビリティビジネス経営研究会
2024.02.07
業績アップコンサルタントコラム
【中古車販売店の会社様必見!】中古車販売で業績を急成長さ…
いつもお世話になっております。 船井総合研究所モビリティ支援部の濱口です。 いつもメルマガをご愛…
MORE
-

文野 陽太
2024.01.31
業績アップコンサルタントコラム
〈申込締切迫る〉中古車販売店 成功事例セミナーのご案内
いつもお世話になっております。 船井総合研究所の文野でございます。 いつもメルマガをご愛読いただ…
MORE
-

モビリティビジネス経営研究会
2024.01.30
業績アップコンサルタントコラム
直近実績好調な中古車販売店が行っている事例3選をご紹介
2月に入り、自動車業界の需要期も残り2ヶ月となりました。 2024年10月から支払総額義務化が始…
MORE
-

モビリティビジネス経営研究会
2024.01.29
業績アップコンサルタントコラム
【中古車販売店の会社様必見!】中古車販売で業績を急成長さ…
いつもお世話になっております。 船井総合研究所モビリティ支援部の濱口です。 いつもメルマガをご愛…
MORE
-

文野 陽太
2024.01.24
業績アップコンサルタントコラム
中古車販売店 成功事例セミナーのご案内
いつもお世話になっております。 船井総合研究所の文野でございます。 いつもメルマガをご愛読いただ…
MORE
-

モビリティビジネス経営研究会
2024.01.24
業績アップコンサルタントコラム
【中古車販売店の会社様必見!】中古車販売で業績を急成長さ…
いつもお世話になっております。 船井総合研究所モビリティ支援部の濱口です。 いつもメルマガをご愛…
MORE
-

淵上 幸憲
2024.01.23
業績アップコンサルタントコラム
【大人気の定番セミナー!2月22日(木)弊社:丸の内オフ…
いつも弊社のメルマガをお読みいただいている皆様 ありがとうございます。 私、モビリティ支援部/フ…
MORE
-

松原 潤
2023.12.25
業績アップコンサルタントコラム
【ガソリンスタンド向け】油外収益強化レポート!成功事例の…
いつもメルマガをご覧いただきありがとうございます。 モビリティ支援部の宮原です。 本日は、ガソリ…
MORE
-

モビリティビジネス経営研究会
2023.12.20
業績アップコンサルタントコラム
新車リース販売店が繁忙期を攻略するために①
平素よりお世話になっております。 船井総合研究所 モビリティ支援部の遠藤です。 日頃は全国の新車…
MORE
-

文野 陽太
2023.12.20
業績アップコンサルタントコラム
【中古車販売店向け】軽中古車専門店の2023年振り返り
いつもお世話になっております。 船井総合研究所の文野でございます。 いつもメルマガをご愛読いただ…
MORE
-

陳屹鈞
2023.12.19
業績アップコンサルタントコラム
【必見】軽中古車販売店で成約率を向上させるポイント大公開…
いつもお世話になっております。 モビリティ支援部の陳です。 いつもメルマガをご愛読いただき、 誠…
MORE
-
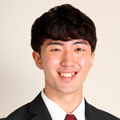
宮原 拓司
2023.12.18
業績アップコンサルタントコラム
【ガソリンスタンド向け】油外収益強化レポート!成功事例の…
いつもメルマガをご覧いただきありがとうございます。 モビリティ支援部の宮原です。 本日は、ガソリ…
MORE
-

モビリティビジネス経営研究会
2023.12.12
業績アップコンサルタントコラム
2023年軽中古車専門店成功事例レポート
いつもメルマガをご愛読いただき、ありがとうございます。 船井総研 濱口でございます。 本日は、 …
MORE
-

新村 雅也
2023.12.05
業績アップコンサルタントコラム
油外収益強化レポート!事例企業のご紹介!
いつもメルマガをご覧いただきありがとうございます。 モビリティ支援部の新村です。 本日は、ガソリ…
MORE
-

モビリティビジネス経営研究会
2023.11.21
業績アップコンサルタントコラム
2023年軽中古車専門店成功事例レポート
いつもメルマガをご愛読いただき、ありがとうございます。 船井総研 濱口でございます。 本日は、 …
MORE
-

淵上 幸憲
2023.11.20
業績アップコンサルタントコラム
【業界急成長中!!】 コーティング事業の成長を加速させる…
いつもブログをお読みいただきましてありがとうございます。 船井総合研究所 モビリティ支援部 マネ…
MORE
-

新村 雅也
2023.10.19
業績アップコンサルタントコラム
【新車リース】全国モデルスタッフ3名の商談術大公開!
いつもお世話になっております。 船井総合研究所の新村です。 本日は新車リース販売店の 全国モデル…
MORE
-

淵上 幸憲
2023.10.18
業績アップコンサルタントコラム
【12月5日(火)】東京開催!モビリティ業界のM�…
いつもブログをお読みいただいている皆様、 本当にありがとうございます。 船井総合研究所の淵上幸憲…
MORE
-

森 祐輝
2023.10.17
業績アップコンサルタントコラム
【最新】2023年新車リースヒット最新事例特集!
平素よりお世話になっております。 船井総合研究所 モビリティ支援部の森です。 いつも弊社メルマガ…
MORE
-

加藤 智
2023.10.10
業績アップコンサルタントコラム
<新車販売店向け>全国の契約満了事例から見る 「マイカー…
平素よりお世話になっております。 船井総合研究所 モビリティ支援部 リーダーの加藤智です。 本日…
MORE
-

モビリティビジネス経営研究会
2023.10.10
実況中継コンサルタントコラム
新車リース時流予測セミナー
2023年10月2日(月) 株式会社船井総合研究所 丸の内オフィス 2023年10…
MORE
-

服部 憲
2023.10.04
業績アップコンサルタントコラム
顧客名簿5,000件以上ある企業ほどデータに基づくCRM…
コンサルタントコラムをお読み頂いている皆様、いつもありがとうございます。 船井総合研究所 モビリ…
MORE
-

新村 雅也
2023.10.02
業績アップコンサルタントコラム
【最新事例公開】新車リース集客アップ事例!
いつもお世話になっております。 モビリティ支援部の新村です。 本日は新車リース販売店の 最新集客…
MORE
-

モビリティビジネス経営研究会
2023.09.28
実況中継コンサルタントコラム
新車リース営業力アップセミナー
2023年9月1日(金) 株式会社船井総合研究所 丸の内オフィス 2023年9月1…
MORE
-

平井 鴻希
2023.09.28
業績アップコンサルタントコラム
来店誘導率を高め売り上げアップ
いつもコラムをお読みいただいている皆様、 ありがとうございます。 船井総合研究所の平井鴻希です。…
MORE
-

堀 和紀
2023.09.28
業績アップコンサルタントコラム
「DX」を通じて事業責任者の管理力を向上させませんか?
いつもお世話になっております。 船井総合研究所モビリティ支援部の堀です。 昨今、「DX」や「デジ…
MORE
-

モビリティビジネス経営研究会
2023.09.22
実況中継コンサルタントコラム
<モビリティビジネス研究会 車検アカデミー>
2023 年 9 月 8 日(金)東京本社 2023 年 9 月 8 日(金)船井総合研究所 東…
MORE
-

疋田 詩織
2023.09.19
業績アップコンサルタントコラム
◥◣自動車業界向けDX◢◤ 「うちにはIT、デジタルが分…
いつもお世話になっております。 船井総合研究所モビリティ支援部の疋田です。 自動車販売店の運営で…
MORE
-

新村 雅也
2023.09.13
業績アップコンサルタントコラム
新車リースで新規集客にお悩みの方は必見です!
平素よりお世話になっております。 船井総合研究所の新村です。 本日は新車リース店で新規客を年間4…
MORE
-

平井 鴻希
2023.09.13
業績アップコンサルタントコラム
中古車からの業態転換!年間200台以上新車を販売する店舗…
いつもお世話になっております。 船井総合研究所モビリティ支援部の平井です。 今回のコラムでは三重…
MORE
-

曽根 翼
2023.09.05
業績アップコンサルタントコラム
少しでもDXに興味がある/知りたい方は是非お読みください
いつもお世話になっております。 船井総合研究所モビリティ支援部の曽根です。 今日、WEB、SNS…
MORE
-

田村 達朗
2023.08.29
業績アップコンサルタントコラム
【輸入車販売店の会社様必見!】輸入車販売で業績を伸ばし続…
いつもお世話になっております。 船井総合研究所モビリティ支援部の田村です。 いつもメルマガをご愛…
MORE
-

田村 達朗
2023.08.29
業績アップコンサルタントコラム
【輸入車販売店の会社様必見!】輸入車販売で業績を伸ばし続…
いつもお世話になっております。 船井総合研究所モビリティ支援部の田村です。 いつもメルマガをご愛…
MORE
-

田村 達朗
2023.08.29
業績アップコンサルタントコラム
【輸入車販売店の会社様必見!】輸入車販売で業績を伸ばし続…
いつもお世話になっております。 船井総合研究所モビリティ支援部の田村です。 いつもメルマガをご愛…
MORE
-

加藤 智
2023.08.28
業績アップコンサルタントコラム
「フラット7」で販売台数4年連続日本一を達成! 新車リー…
いつもお世話になっております。 モビリティ支援部の加藤です。 今回のコラムでは、沖縄県浦添市に本…
MORE
-

田村 達朗
2023.08.23
業績アップコンサルタントコラム
【輸入車販売店の会社様必見!】輸入車販売で業績を伸ばし続…
いつもお世話になっております。 船井総合研究所モビリティ支援部の田村です。 いつもメルマガをご愛…
MORE
-

モビリティビジネス経営研究会
2023.08.10
実況中継コンサルタントコラム
<整備工場の生産性向上事例大公開セミナー>
2023年7月18日(火)東京本社 2023年7月18日(火)、船井総合研究所 東京本社にて、「…
MORE
-

森田 光輝
2023.08.04
業績アップコンサルタントコラム
【必見】WEB集客の費用対効果を改善させる事例大公開!
いつもメルマガをご愛読いただきありがとうございます。 モビリティ支援部の森田です。 本日は自動車…
MORE
-

平井 鴻希
2023.08.04
業績アップコンサルタントコラム
【営業に悩む方必見!】業界未経験から早期に成約率60%を…
いつもメルマガをご愛読いただきありがとうございます。 モビリティ支援部の平井です。 本日は新車リ…
MORE
-

モビリティビジネス経営研究会
2023.08.02
実況中継コンサルタントコラム
<モビリティビジネス経営研究会 車検アカデミー>
2023年7月14日(金)東京本社 2023年7月14日(金)、船井総合研究所 東…
MORE
-

文野 陽太
2023.07.27
業績アップコンサルタントコラム
軽中古車専門店会のご案内
いつもメルマガをご愛読いただき、ありがとうございます。 船井総研 文野でございます。 本日は、 …
MORE
-

曽根 翼
2023.07.25
業績アップコンサルタントコラム
カーディーラーにおけるDXの取り組み事例
「DX」という言葉が出始めた当初は「デラックスではありませんよ」という 話から「DXとは」という…
MORE
-

文野 陽太
2023.07.25
業績アップコンサルタントコラム
【中古車販売店向け】5~7月成功事例レポート
いつもメルマガをご愛読いただき、ありがとうございます。 船井総研 文野でございます。 本日は、 …
MORE
-

加藤 智
2023.07.24
業績アップコンサルタントコラム
【新車販売店の店長・営業スタッフ必見!】 赤字続きだった…
平素よりお世話になっております。 船井総合研究所の加藤智です。 本日のコラムは、 毎月の営業赤字…
MORE
-

加藤 智
2023.07.24
業績アップコンサルタントコラム
割賦払い時の成約率をグンと高める方法
平素よりお世話になっております。 船井総合研究所の加藤智です。 今回は自動車販売店が 割賦払い時…
MORE
-

加藤 智
2023.07.13
業績アップコンサルタントコラム
【新規集客のコツがわかる!】 日本一達成店舗の成功ノウハ…
平素よりお世話になっております。 船井総合研究所の加藤智です。 6月も終わり、1年の半分が過ぎま…
MORE
-

新村 雅也
2023.07.11
業績アップコンサルタントコラム
【営業力に悩む方必見!】新車リースで年間200台以上販売…
いつもメルマガをご愛読いただきありがとうございます。 モビリティ支援部の新村です。 本日は新車リ…
MORE
-

淵上 幸憲
2023.07.11
業績アップコンサルタントコラム
【即成果に繋がる事例紹介】 夏対策商品を提案して収益性ア…
いつも弊社コラムをお読みいただいている皆様、 いつもありがとうございます。 船井総合研究所の淵上…
MORE
-

新村 雅也
2023.07.05
WEB集客コンサルタントコラム
【SNS集客】新車リース店のSNS活用の集客手法をお伝え…
いつもメルマガをご愛読いただきありがとうございます。 モビリティ支援部の新村です。 本日は新車リ…
MORE
-

モビリティビジネス経営研究会
2023.07.05
実況中継コンサルタントコラム
<モビリティビジネス経営研究会 車検アカデミー>
2023年6月13日(火)オンライン 2023年6月13日(火)、船井総合研究所 …
MORE
-

熊谷 敬徳
2023.07.03
業績アップコンサルタントコラム
◥◣自動車業界向け◢◤ 今どき賃金制度について!
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。 船井総合研究所の熊谷敬徳です。 先週に引き続き、本…
MORE
-

曽根 翼
2023.07.03
業績アップコンサルタントコラム
【必見】実は今の”チャットボット”は進化しています
自動車販売店様、自動車整備工場様に合ったデジタルツールがあり、それを是非今回はご紹介させていただ…
MORE
-

新村 雅也
2023.06.30
業績アップコンサルタントコラム
自動車販売店向けLINE活用で集客アップ事例大公開!
いつもメルマガをご愛読いただきありがとうございます。 モビリティ支援部の新村です。 本日は自動車…
MORE
-

新村 雅也
2023.06.28
業績アップコンサルタントコラム
【SNSで集客アップ!】新車リース店向けInstagra…
いつもメルマガをご愛読いただきありがとうございます。 モビリティ支援部の新村です。 本日は新車リ…
MORE
-

モビリティビジネス経営研究会
2023.06.28
業績アップコンサルタントコラム
◥◣自動車業界向け◢◤ 今どき賃金制度について!
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。 船井総合研究所の熊谷です。 これまで多くの企業にて…
MORE
-

モビリティビジネス経営研究会
2023.06.26
実況中継コンサルタントコラム
【実況中継】モビリティビジネス経営研究会(普通車専門店会…
2023年6月19日(月)に「モビリティビジネス経営研究会」が開催されました。 今回は普通車専門…
MORE
-

モビリティビジネス経営研究会
2023.06.22
業績アップコンサルタントコラム
【初開催】グーネット×船井総研 グーネット集客を倍増させ…
本日は2023年7月20日(木)に”初開催”となる、株式会社プロトコーポレーション様(グーネット…
MORE
-

加藤 智
2023.06.21
業績アップコンサルタントコラム
日本一を達成した販売店の成功ポイント3選
平素よりお世話になっております。 船井総合研究所の加藤智です。 本日は、本年2月に配信しご好評を…
MORE
-

齊藤 浩太
2023.06.21
業績アップコンサルタントコラム
自社の入店見積率を見てますか?そこを強化するだけで売上が…
コンサルタントコラムをお読み頂いている皆様、いつもありがとうございます。 船井総合研究所の齊藤浩…
MORE
-

加藤 智
2023.06.16
業績アップコンサルタントコラム
間違えてはいけない!チラシの効果を見極めるポイント
平素よりお世話になっております。 船井総合研究所の加藤智です。 今回は皆様のような自動車販売店が…
MORE
-

新村 雅也
2023.06.15
業績アップコンサルタントコラム
【ガソリンスタンド必見!!】 ガソリンスタンドが新車リー…
いつもメルマガをご愛読いただきありがとうございます。 株式会社船井総合研究所の新村です。 本日は…
MORE
-

加藤 智
2023.06.02
コンサルタントコラム
【社長特別インタビュー掲載】 年間45台販売だった整備工…
平素よりメルマガのご愛読ありがとうございます。 ㈱船井総合研究所 モビリティ支援部の加藤智でござ…
MORE
-

文野 陽太
2023.06.01
業績アップコンサルタントコラム
即決率を高めるための重点項目
株式会社 舩井総合研究所の文野でございます。 本日は「即決率強化」と題しまして、 営業面の施策に…
MORE
-

加藤 智
2023.05.31
業績アップコンサルタントコラム
【特別インタビュー掲載!】 コロナ禍でも売上122%成長…
平素よりメルマガのご愛読ありがとうございます。 ㈱船井総合研究所 モビリティ支援部の加藤智でござ…
MORE
-

曽根 翼
2023.05.31
業績アップコンサルタントコラム
ホームページ問合せからの来店率が40%未満の会社様は、そ…
いつもコラムをお読みいただいている皆様いつもありがとうございます。 船井総合研究所の曽根翼です。…
MORE
-

遠藤 圭太
2023.05.24
業績アップコンサルタントコラム
整備入庫客アプローチからの販売台数アップ手法
いつもお世話になっております。 船井総合研究所の遠藤圭太でございます。 日頃は新車リース業態を中…
MORE
-

モビリティビジネス経営研究会
2023.05.17
実況中継コンサルタントコラム
【実況中継】整備士向け!先輩社員研修
2023年5月16日(火)、船井総合研究所 東京本社にて、「整備士向け!先輩社員研修」が開催され…
MORE
-

平井 鴻希
2023.05.16
業績アップコンサルタントコラム
Instagram広告の活用で問い合わせ数アップ!
コンサルタントコラムをお読みの皆様、いつもありがとうございます。 船井総合研究所の平井鴻希です。…
MORE
-

新村 雅也
2023.05.15
業績アップコンサルタントコラム
【繫盛店レポート】新車リースで年間400組以上の新規集客…
平素よりお世話になっております。 船井総合研究所の新村です。 皆様、新規集客は伸びておりますでし…
MORE
-

田村 達朗
2023.05.11
自動車販売コンサルタントコラム
AA相場が下がり始めた今、徹底すべき在庫管理数値
いつも大変お世話になっております。 船井総合研究所の田村達朗です。 早速ですが本日は車販売店にお…
MORE
-

齊藤 浩太
2023.05.11
業績アップコンサルタントコラム
【トップ営業スタッフ育成フォーラム】全国のトップ営業マン…
いつもお世話になっております。 船井総研の齊藤です。 本日は軽中古車販売店で「年間300台以上販…
MORE